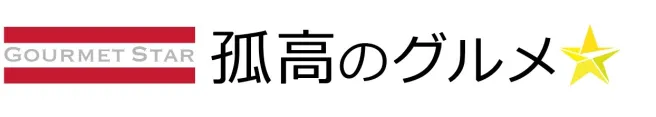四ツ谷『すし匠 斎藤』がミシュランを獲れない理由?/安いまな板
四谷『すし匠』のレビューを読まれた方から赤坂見附『すし匠齋藤』も頼むと言われたのでこちらのレビューをもって回答と致します。
すし匠からキラ星の如く色々なお店が出ておりますが、その中でも1番人気のこちらのお店。
駅近くのビル内にあるのですが、靴を脱いで掘り炬燵のような形でカウンターに横並びで座るスタイルです。
夜35,000円/人〜、昼30,000円/人で握り鮨とツマミが交互に出るスタイルは本店と変わらず。お酒はあくまで日本酒ということで、お酒を3-4杯楽しんで2-3カンお代わりして、大体42,000-45,000円/人程。
〜お客さんに思いっきりリラックスして楽しんで握り鮨を食べてもらいたい〜
これは今はハワイで奮闘されている創業者の中澤圭二氏の教えを忠実に守っているからでしょう、すし匠の店内はどこもいつでも活気があります。
刺身や鮨ネタの1つ1つのレベルは『すし匠』のほうが1-2段階上ですが、酢飯(シャリ)とのバランスやつまみの味付けの創意工夫においては『すし匠齋藤』が1-2段階上。結果的に総合力はほとんど変わらないので、予約が取れたほうに行く、どちらのお店も好きという方が多いです。
この日個人的に当たりだったのは、鮑の切り身とヒラメの刺身のハラペーニョソース和えや金目鯛の柚子胡椒ポン酢和えに毛蟹の内子の塩漬けソースがかかった茶碗蒸し。
鮑の切り身は蒸し上げたまだ温かな鮑の切り身をそのまま塩や山葵で頂くという味付けは極めてオーソドックスなものですが、切り方が素晴らしい。大きな黒鮑の縦幅横幅を目一杯活かして5-7mm幅で大きな切り身にして出して下さいます。私は今や日本の大定番となった鮑を大根の酵素で柔らかくしてそこから低温調理で蒸しあげること自体には大賛成なのですが、とかく世間ではその柔らかさをアピールしたいがために分厚く出されることが多いので、こういった工夫は好みです。
ヒラメの刺身のハラペーニョソースに関しては、最初に一口ハラペーニョソースの青唐辛子部分を口に入れたらしっかりと青唐辛子の辛味があったので、これはヒラメとの組合せは相当厳しいのでは?と思っていたのですが、口に入れたらなんのその。大きく薄く切り出したヒラメの刺身の水分量がとても多いので、口の中で見事にバランスが取れていました。通常、お刺身を頂く際の感想として、「みずみずしい」というのはNG表現で、私もこのヒラメだけをこのレベルのお鮨屋で頂いていたら水っぽくてマイナスの印象でしかありませんでしたが、意図した通りなのでしょう、このソースとの合わせ方はお見事でした。
金目鯛の柚子胡椒ポン酢和えもこちらは四谷『すし匠』でも頂きますが、ちゃんと完熟した柚子を使った柚子胡椒を使っているので、ポン酢との香りがとても合っていました。
毛蟹の内子をソースにして茶碗蒸しの上にかけて蒸した一品。滑らかな茶碗蒸しに濃厚な毛蟹の内子の味が見事に掛け合わされて、これだけは別格別次元のミシュラン三つ星レベル。
それと、蒸したばかりのサイズも味も見事な毛蟹の身と蟹味噌を大ぶりな織部焼きの鉢の中で少なめの酢飯(シャリ)と合わせて手巻きにして来店者1人1人に食べさせるパフォーマンスや控えめにした酢飯(シャリ)とのバランスも見事です。
酒蒸し蛤もこのサイズと味は素晴らしい。
翻って、こはだ/かすご/アジ/鯖/鮪の赤身などの地味な江戸前の鮨ネタはこのクラスのお鮨屋では並レベル。
要所要所の目立つ大ネタにしっかりコストをかけ、来店者を驚かせ満足させる手腕はこちらのお店の客層の心理をよく理解していて見事です。
鮪は赤身のレベルは一目で判るほどとても低いのですが、それ以外はとても良いです。赤身の良さまでこだわると本鮪というのはとてつもない値段に跳ね上がってしまうので、あくまで客層の好みに合わせて中トロ以上の良さを引き出すことに専念している印象です。
酢飯とのバランスも四谷『すし匠』よりはずっと良く、
「はがし」という赤身と中トロの間の部位や「おはぎ」という本店と同じ骨身の分を貝で削り出した部位など、そのままでは食べれないもしくは口当たりの悪いスジを取り除くなどして色々と工夫して愉しませてくれます。
こちらのお店を好きという方は、お能やオペラ鑑賞よりも歌舞伎やディズニーランドが好き、ヨーロッパ旅行よりもハワイが好き、クラシック音楽鑑賞よりもポップミュージシャンのコンサートが好きという方が多いと思います。
これは決してどちらが良い悪いということではなく、食の好みは本人が意図しないうちに色々な分野に相互に影響し合っているということを申し上げたいだけです。すし匠系列の握り鮨は蒲田『初音鮨』同様に、その他の鮨慣れしていない外国の方々の受けや若者への受けもとても良いと思います。
多くの来店者は自分に色々尽くしてくれて会話が途切れないよう賑やかに振る舞ってくれてというほうが良いわけで、多くの来店者は銀座『すきやばし次郎』や銀座『よしたけ』で静かにじっくり美味しく目の前の鮨と向き合うよりも賑やかで楽しいほうを選ぶからです。
眼の前のお客様に目一杯楽しんでもらいたいという今はハワイ店で奮闘されている御主人の薫陶を見事に受け継いだ四谷『すし匠』と赤坂『すし匠齋藤』の御主人のスタイルは今のままで良いのですが、より高みを目指されるのであれば5点、私の主観ではありますが、提案があります。
----------------------
1.山葵の擦り方が直線的で上手ではない
2.まな板にもう少し敬意を払うこと
3.まな板の高さが低過ぎるて料理人達の所作や動線に難あり
4.上から見下ろすかのような配膳スタッフ
5.洋物の調味料を使うななら、ワインへももう少し注力
---------------------
「1.」に関しては、良い山葵とせっかくのおろし板なのですから、おろし板の中央部分だけを直線的に腕力でゴシゴシ使わず、全体を円で使うようにしたらもう少し山葵の細胞が潰れず均一に空気に触れて美味しくなると思うからです。
「2.」に関しては、私はここを最も注視しているのですが、席の構造上しょうがないとはいえ、まな板の上に両手をついて来店者と会話したり、刺身などを切ったりする場所にあとの来店者達のためのつまみなどの器を乗せて並べる点は大きく問題ありだと考えます。正直、私はこの所作には今のすし匠齋藤の色々な部分が集約されて現れているようでとても嫌ですね。お鮨というのは人間が生身の手で生魚を握って出すという世界水準から見れば極めて特異な料理になるわけです。これが成り立つのも過去から現代にかけての数多の鮨職人の方々の圧倒的な衛生に対する意識の高さの賜物でしょう。そういった事を踏まえるととても高次元のお鮨屋とは思えない所作だと思います。
「3.」内装をゼロから創り上げるのはとても難しいことは私も自宅や別荘で経験しているので重々理解しています。センチメートル単位の違いで全く空間の印象が変わるからです。そういう意味では職人の方々にとっては今の付け場(調理場)は5-7cm低いようです。ここが低いが故に、鮨ネタを切る際に腰が引けてしまい、刺身と正対出来なくなっており、且つ、後ろを通る方が大変そうです。そして結果的にまな板の上に両手を付いたりといった余分な所作が生まれていますので、次の内装工事の際はご参考下さい。白木のカウンターも毎日洗って拭いてを繰り返した方が良いです。今は早急にグラインダーをかけるべき。
「4.」これはあくまで私の好みではありますが、せっかく掘り炬燵式のカウンターにして、それに合わせて調理場の高さも整えて空間をできるだけ天井を高く見せるためにその他を『低く』統一しているのに来店者の後ろに立つ肝心の配膳スタッフが立ったままというのは少し違和感があります。膝立ちもしくは椅子に座っても良いのではないかと思います。しっかりと教育されている配膳スタッフが立つことによってチグハグさを生んでいるとしたらもったいないです。
「5.」は典型的な江戸前鮨ではなく、ところどころに洋物の調味料などを使用されるのであればワインももう少しまともな品揃えにされたら良いのでは?と思うからです。今のままではせっかく本店よりと攻めた美味しいツマミを作ってもそこで止まってしまうからです。私は日本酒が大好きなので今のままでも充分良いですが、ミシュランスタッフを筆頭とした欧米人目線は異なります。ただ、つまみへのスタイルが異なるので、四谷『すし匠』にはこのような提案はしません。青は藍より青いのですから、もし今後も攻めたつまみを所々に出されるのでしたら、ワインも是非お願いしたいですね。
久しぶりに伺った四谷『すし匠齋藤』は相変わらず素敵なお店でしたが、以前のような肝心なところはピシッと締めている良い意味の緊張感が全体の3割ほどのお料理になく、雰囲気も少しダラけ気味でした。シャーベットの慣らしの工程を1-2回減らしたのではないでしょうか?シャーベットの口当たりも四谷『すし匠』よりも数段落ちていました。アイス最中は衣の薄さと焼き目とのバランスが絶妙でした。
これは今の四谷『すし匠』も同様なのですが、創業者の中澤圭二氏の教えから少し脱線気味の雰囲気がところどころに出ているのが気になります。30代40代でコロナ禍もモノともせずこれだけ成功すれば、どんな人間でも程度の差こそあれ、脱線気味になるのは当然なのですが(そもそも大半の方々は有頂天になって脱線してしまうのですが)、ここは双方の御主人方は踏ん張りどころかなと思います。
大半の方々は意識されていませんが、本物のグルメンにとっては、「美味い」と「旨い」、「匂い」と「臭い」などは明確に違うんですよね。
『失敗の本質』という本の教訓ではありませんが、私のような人間が気付いているだけの段階で修正されたほうが後がですよー。
今のままでも充分大繁盛店なので良いのでしょうが、より高みを目指されるのでしたら、他店にもちゃんと定期的に足を運んで良い点は学んで吸収して、自分達のコースももう一度まっさらな気持ちで見直して、ズレた誤差を微調整する。もしこの辺りを改善されたらお2人が望むより高いその場所へ到達できると思います。
カジュアル接待や友人もしくはデートに。
※どんなシチュエーションにせよ、こちらに来られる方は日本酒を愉しめる方が圧倒的に良いです。
※私の印象に残ったお皿もつまみのほうが圧倒的に多いことからも、すし匠齋藤を鮨屋として括る方が無理があるかも?
※今回は写真が特に下手で申し訳ありません。
※早急に白木のカウンターを綺麗にして欲しいです。