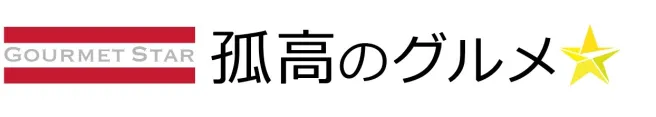南青山『4000Chinese』超デート用/オーナーの魅力/戦略と一貫性
その環境の良さから近年どんどん美味しいお店が増えている日赤通り沿いにあるお店です。
いいですよねー、日赤通り。
決して道幅広くないのにあの重要なところが良いです。
六本木通りから日赤病院に行くまでの日赤通りの東西が住所が分かれている点も個人的には好きですね。西が南青山で東が西麻布、日赤病院まで南下するとあとは全部広尾のこの感じ。
以前この界隈(南青山側)に住んでましたがとても気に入ってました。最近は新しいマンションが増えてどんどんお店も人口も増えてきてます。
こちらのお店が2018年12月にOpenして、その後2019年に亀戸『鳥さわ』が進出してから急に東京カレンダー臭がしだしましたがそれはそれ。
あるときは恵比寿から、あるときは広尾から、またあるときは表参道や六本木から、個人的によく通る道の1つです。
友人「お盆って食べ物難民になるでしょ?家庭のことはしっかり終わらせてから行くからさ、ランチでどっか行かない?『4000Chinese』はどうかな?」
僕「いいねー、いこう×2♬」
いいですねー、カウンター材は表面塗装されているけど落ち着いた色合いで高級感あって、カウンターの奥行きや椅子の椅子の座り心地なども良い。
さて、オーナーはかの四川飯店でずっと陳建一氏をサポート/supportされていた菰田 欣也/Komoda Kinyaシェフですね。
漫画キングダムの王輝将軍と俳優の伊武雅刀氏を足して2で割ったようなあの眼光はご健在。
個人的には最初に氏が満を辞して独立されるときに、まず火鍋のお店をOpenされると聞いて唸ったものです。
なるほど、いきなり高級路線のご自分のお店からスタートせず、オペレーション/operationの簡単な店舗展開できるお店から始められるのか。しっかり経営のポートフォリオ/portfolio意識してるなー、すごく緻密で慎重だなー。これはいよいよ本気だなー、そのうちご自分の高級路線のお店も出店されるんだろうなー。
で、そちらがある程度軌道に乗ってからの南青山『4000Chinese』のオープン。
早いものでまもなく丸4年。
お店のオープン日と僕の誕生日が同じなのでよく覚えてます。
全然関係ないけど、都営大江戸線も年は違えど同じ日。
本日もお盆なのにお昼からカウンターは満席です。
お料理は2コースありましたが、22,000円/人のほうを注文。そこに今日はアルコール/alcoholは無しでと固く誓い合った我々は、中国茶のペアリング(6,000円/人)をつけていたのですが、途中でテンション上がって結局ワインまでお願いしてしまいました、やだ恥ずかしい(//∇//)
さてお料理です。
〈冬瓜/とうがん/winter melon〉
冷たい前菜です。
こちらは1番下にはカボスをしっかり効かせた柔らかいゼリーを敷き、その上に冬瓜と干し海老の出汁を合わせたとろみのあるソースをかけ、中央に中の酸味が広がるように横に切られた青いニュアンスの強いトマトと島エビのお刺身が添えられています。
説明では「酸辣湯/サンラータン」のようといわれましたが、個人的には「辣(ラー)」を感じない洗練上品なお味でしたのでそうは思わず。混ぜてお召し上がりくださいといわれたものの、和食やフレンチが大好きな僕としては最初から混ぜるなどと無粋なことはできず、それぞれを個別に味わってから最後に全部混ぜて頂きました。
暑い日でしたがこの一品でスッと全身の熱が消え、涼やかな気持ちに。
さて!?
〈金華豚/pork〉
異なる大きさのひき加減と種類の胡椒/pepperを擦り込んだ金華豚の焼き豚/チャーシューです。
こちらは意図的に赤身の筋肉部分を食べさせるように調理されています。
本場中華ならではの香辛料をほとんど使われていないので、豚肉の筋肉質な旨味と胡椒/pepperとのバランスに集中できます。
味変で豆板醤×パプリカのソース。
パプリカは一旦焼いて甘みを出して、丁寧に外側向いてから豆板醤の塩味や辛味とぶつけたのかな?
うん、やっぱり日本人が作る高級中華料理ならではの安心感があるな、今日を良い感じに楽しめそう♬
〈乾物/soup〉
様々な乾物をお店の基礎スープである上湯/シャンタンと共に壺もしくは鍋に入れて、一切の蒸気を漏らさずに蒸気の対流で加熱していくいわゆる一つの佛跳牆(ぶっちょうしょう/フォーティャオチァン)、修行中の僧侶すら修行を中断して飲んでしまうほどの美味しいスープというのが名前の由来。
元々は中国福建省の名物料理ですが、今では広東料理を筆頭に中国の高級料理店では愉しめる一品です。
通常であれば具材の少なさや単純構成された風味からこれはただの乾物スープじゃん!という名ばかりの薬膳スープが多いですが、4000Chineseではただの謙遜だと理解できます。フレンチなどの琥珀色の極上コンソメスープに対抗する中華料理は佛跳牆(ぶっちょうしょう/フォーティャオチァン)だと再認識。視認できる食材だけでも干しアガリスク茸/干し海鼠(なまこ)/帆立の貝柱/牛の腱/干し鮑(あわび)/乾燥させたクコの実/各きのこの乾物などなど、そこにお店の上湯(シャンタン)/干しエビ/豚/鶏/牛赤身/白菜などの旨味が加わり、蠱惑的で複雑健康的な濃縮天然アミノ酸の黄金色の液体の素晴らしさにしばし目を瞑ります。
もしかしたらその数秒間だけは煩悩だらけの僕のお尻は座面から数センチ浮いていたかもしれません。琥珀色のスープ/soupを噛むように一口一口ゆっくり堪能。思わずスープをすくう動きを遅くさせます。
うーん、このレベル提供されたら、良い意味でお茶のペアリングいらないや(笑)
あれ?カウンター奥に大量の松茸がある。
僕が見慣れた松茸とちょっと形が違うなー、でも立派だなー。
もう松茸などの豪華食材を率先して食べたいとは思わなくなったすれっからしの僕ですが、やっぱり眼にすると心ときめきます。
<加藤ポーク/pork>
菰田シェフは中華らしい鮮やかな色の使い方が上手だと思います。
なんで?
それはおそらく店内内装のベースになっている輪島塗りの卓上膳/ランチョンマット。
日本の朱色ではない、輪島塗り独特の深い赤をベースに組み立てているので、いかにも中華な印象を与えることなく、その赤の色調に対してのお皿、盛り付けに迷うことがないわけです。
木製漆器に珪藻土ペーストをたっぷりつけた布を巻いて、そこに何十回も漆を薄く重ねて総工程数100以上かけて頑強性を飛躍的に高めたのが輪島塗の特徴ですが、その珪藻土は今から2000万年以上のまだ日本列島がアジア大陸/亜大陸から観音開きに分裂してその割れ目にフィリピンプレートの火山諸島が大量に衝突してフォッサマグナとなり、やっと今でいう千葉県/房総半島ができて、にも関わらずまだ九州が韓国と繋がっていた頃に、今でいう日本海エリアの海水が停滞して藻やプランクトンが大量発生して死んで、それが土化したのが起源だということは、珪藻土マットをお使いの足元衛生に敏感な方々は日々それを踏んでいるのだということはここだけの話です。
一見中華食器のようで、それらもあるものの、印象的な器には大陸の影響を受けて大きく発展した有田焼の器が使われているのも日本人である中華料理人としての矜持でもあると思います。
話を戻します。
こちらは簡単に申し上げると「酢豚」。オレイン酸多めの口の中で脂身の甘さ立ってとろける外側の適切な焼き目というメイラード反応によってぎりぎりその形状を保っている角切りの豚肉が、酸が熱で少し飛ぶことによって赤ワインビネガーのニュアンスも含んだ高級黒酢ソース/sauceにコーティング/coatingされ、周辺にはゴーヤやスライスして乾燥させたオレンジなどと一緒にお皿に盛り付けられています。そしてその上からベージュ/beigeのナッツやグリーン鮮やかなピスタチオがたっぷり振りかけられ、丁寧に飼育された豚肉特有の甘味に色鮮やか酸味鮮やかアクセントばっちりなお洒落な酢豚。
カウンターから口々に、
「すみません、やっぱり赤ワインください!」
提供されたのはギリシャの赤「ディアポロス 2017年 キリ・ヤーニ」。ギリシャ固有の品種であるクシノマヴロ87%にシラー13%です。余談ですがクシノマヴロはギリシャ語で「酸と黒」の意味を持ちます。スパイシーで僅かにストロベリー/strawberryや薔薇/Roseのニュアンスnuance。わー、この温度での提供いいなー、グラスの中で7-8度位?ここから飲み始めれるのは幸せです。さー、あと2-3度上がる数分後に開け!
うーん、洗練されたこちらのお店らしい酢豚だなー、ワインとも合って美味しいです。
<点心/>
次は小籠包です。
一段目は黒、二段目は赤。
一段目の黒いほうはイカ墨の黒で、上からたっぷり黒トリュフをかけて頂きます。オーストラリア産っていってたかな?
二段目の赤は辣油/ラー油の赤。ピリッとしますが舌の上には長く残らず、純粋に2つの小籠包を飽きずに頂けます。
<モウカザメ/毛鹿鮫>
このお料理で菰田シェフの謙遜さが確定。
煩悩の塊で傲岸不遜な僕でしたら料理名は<フカヒレ>にしている、そんなお品。
知的聡明グルメンな皆様ご存知の通り、モウカザメの身ってクセがなくほんのりピンク色なんですが、サッとフライパンで焼くだけでもとてもあっさり白身魚の美味しさを満喫できる、でも食卓では過小評価されている素敵な食材なんですが、このお皿ではその身はほぐれていて、きめ細かく肉厚にカットされたフカヒレに絡みついている程度。
ソムリエ「シェフはモウカザメ/毛鹿鮫のフカヒレしか使わないんです。」
と聞いて、納得至極。
ちゃんと味が残っている毛蟹の身とフカヒレに小さくなったモウカザメと豚肉と毛湯/マオタンあたりのスープ(鶏ガラベース)に発酵させた白菜の葉の部分の風味が溶け込んで餡かけとなったソースが絡みついて、思わず「ハオツー(好吃)/美味しい」、いや、「チャオハオツー(敲好次)/超美味しい」!
あー、すぐに頂くのがもったいない。
繊細で、複雑で、ちゃんと中華してて美味しいなー。
美味しい、美味しいなー、これ。
これがちょっとでも焦げ目の香りや他の鮫/サメの立派な繊維のフカヒレだったら調和が獲れなくなる。このモウカザメのやわらかくきめ細かい繊維だからこそ成立する料理。これは食べるのもったいない、完璧な一品だなー。近年の僕は見た目が派手な料理よりもこういう技ありセンスありのお料理が大好きです。
あ、なんか北京ダックが焼きあがったっぽい。
ふーん、あのサイズあの色で北京ダックねー。
そうか、フカヒレもモウカザメ/毛鹿鮫のヒレだから、食材名としてあのメニュー名で良いのか、さすが。
あれ?でもフォアグラ料理のときは〈フォアグラ〉としていたような?ま、いいや。
<鴨/duck>
北京ダック2本です。
手前が梅ジャムペースト、下が甜麵醬/テンメンジャンの味付けで、お味はいわゆる北京ダック。このスタイルも定番ですね。
東京で頂く北京ダックといえばパレスホテル『琥珀宮』にてとある専門女性に巻いてもらう北京ダックが大好きな僕にとっては、特別な印象はありません。
ただ、それは菰田シェフも承知なわけです。
この北京ダックで特筆すべきはやはり丸ごとダックの見た目インパクトで場がパッと湧くことと、女性が食べやすいサイズに巻かれていることでしょう。
菰田シェフのお料理は徹底してこれ、女性目線。
圧倒的にデート利用されるこちらのお店で、口から沢山のトランプを出すマジック(cards from mouse)のように、かわいくひと噛みした素敵女性の皆さんが、口から北京ダックに包まれている皮や葱/ねぎなどをぶら下げたりこぼしたりして粗相のないように、一口サイズに食べやすく巻かれてあるわけです。
ひょいぱくひと口北京ダック。
コースの位置づけ的にも口休め、箸休め的な位置づけに。
ということはここから?
<鮑/あわび/abalone>
ソムリエが白ワインを用意してくれます。
判ります。
この流れなら、中華でこの流れならジュラ地方のワイン「VIN JAUNE /ヴァン・ジョーヌ(仏語で「黄色いワイン」の意)」でしょう?いいんです、そんなことは判ってます。僕が知りたいのはその先、どの「VIN JAUNE /ヴァン・ジョーヌ」を提供してくれるのか?ってこと。
シャトー・シャロン?
アルボワ ヴァン・ジョーヌ?
コート・ド・ジュラ ヴァン・ジョーヌ?
ヴァン・ジョーヌ・ド・レトワール?
Oh, ” フリュイティエール・ヴィニコル・ダルボワ・アルボワ・ヴァン ジョーヌ/Arbois Vin Jaune ” !?
今日のヴァン・ジョーヌはくるみ系のナッティ/nuttyさやクミン/cuminなどよりもなんだか妙に紹興酒のようなニュアンス/nuanceを感じるなー。
黄色い粒粒ペーストの上にー、黒鮑/クロアワビと先ほどの松茸が縦に割かれてフライ/deep-friedになって、どーん。
Oh,yes、季節的にトウモロコシなのは判るけど、左上には味変用の鮑の肝ソース。
まず、トウモロコシのソース/sauce単体を頂くじゃないですか?そうしたら口の中で急にトウモロコシの味と香りがパッと拡がって、しかも外皮を意図的に濾して取り除いていないので、心地よい食感がプチプチ。で、鮑/あわびの揚げ物にトウモロコシのソース/sauceをつけてパクリ。
パリッ、クニュ、プチプチ、ぐあ~ん。
パリッと揚げらえた塩味の効いた柔らかい鮑/あわびにトウモロコシソースの甘味が加わって、ぷちくにゅ×2ぐあ~ん。
あー、、、
落ち着け、ひとまず次の松茸。
仕切り直してと。
へー、雲南省の松茸ってあんなに大きいんだっけ?
ま、あの辺は土壌豊かだし、なんでも日本よりサイズは大きいか。
パリッ、シャク、シャクシャク、ぷちぷちぷち、ぐあ~ん。
おい×2、雲南省の松茸やべー、、、これ、僕がこう思うってことはプロの料理人の方々でも見分けつく人少ないんじゃ、日本でも丹波あたりの最高レベルの松茸ならそりゃ香りの質が違うから見分けつくけど、とはいえこの雲南産が劣っているわけでなくて、あくまで香りの色調が違うってだけで、今後は中国産と雲南省産の松茸は明確に区別しないと駄目だな、これは。
あ、一周回って冷静になって言い忘れてる、、、
おーいひーっ☆:.。. o(≧▽≦)o .。.:☆!!!!
柔らかい鮑/あわびの海の香りがー、とうもろこしの甘味と合わさってー、衣のパリカリ感ととうもろこしソースの意図的に残されたプチプチ感がー、鮑の塩味とぶつかって昇華されてー、後半からは鮑/アワビの昆布入ってんじゃね?レベルの豆板醤だけ少し混ぜられた豊かなグルタミン酸の旨味で加速してー、拡がってー、海と大地の旨味がー、海と山の旨味がー、大地と山の旨味がー、さらに口の中をお茶でひとすすぎしてから今度は芳醇上品複雑な雲南産松茸の香気がー、縦に割かれたことによって美しい食感そのままにー、さらにそこに食感残されたとうもろこしソースたっぷり絡めちゃったりしてー、鮑/あわびの肝ソースも絡めちゃったりしてー、これがここから無限ループからのぉ〜、空前絶後のぉ~、あ、無くなっちゃった、、、サンシャイン池崎るのここから始まるのに(泣)
ん?
今、僕は座面から少し浮いてませんか?
なんか自分が夜空に浮かんでてカウンターの皆さんの頭頂部が見えるんですけど?
的な錯覚に陥るほどの単純ストレートな食材の組み合わせの美味しさ。
前も同じ感じですと単調に感じるのですが、前のお皿が逆に近いのでより一層このシンプルさが際立ちます。
2つ前の一見あっさりながら複雑深遠なモウカザメ/毛鹿鮫のお皿との対比から味の組み合わせは極めて普通にしながらとても満足度が高いのは、個人的にはとうもろこしの粒皮のぷちぷち感を残して咀嚼する愉しみを付加しているからと思われます。
そう、まさに適切な調理。
そうか夜空のイメージが浮かんだのはこの器からか。
<伊勢海老/spiny lobster>
エビチリ/干焼蝦仁(干烧虾仁)といえば、僕は芝エビなどの小ぶりなエビチリが好きですが、食材の高価さでいえば伊勢海老に勝るものはないでしょう。こちらのお店の豆板醤と濃い赤ケチャップ風味で片栗粉で全体がボタつくことなくソリッド/solidな仕上がり。豆鼓/トウチーいいよね。食べやすいのように尾の身のカットは嬉しいですが、足の付け根はそのままだったので、わざわざ食べるのはやめました。海老好きには堪らない一品。
〈ご飯〉
白米と麻婆豆腐と回鍋肉/ホイコーロー!
美味しい新潟県のつや姫に、別注指定した十勝産マンガリッツァ豚を使った回鍋肉/ホイコーロー。この回鍋肉/ホイコーローは同席したグルメン友人のお陰です。さすが四川飯店な麻婆豆腐ですが、あくまで4000Chineseの戦略にあった、「麻(マー)/花山椒のしびれ」は極力削ぎ落とし、国産牛挽肉の肉と脂の風味と程よい辣(ラー)を愉しむ飯の友という感じ。
うわ、回鍋肉/ホイコーロー最高。
このお肉の皮部分や野菜の厚みの食感が、先程のとうもろこしソースのプチプチ食感と掛かってる。
あー、やっぱりイベリコ系の豚は美味しいなー。
うん、せっかくなので回鍋肉/ホイコーローは独立させてレビュー/reviewしよう。
〈回鍋肉/ホイコーロー〉
皆様はハンガリー/Hungaryに行かれたことはございますか?そうです、東欧のハンガリーです。東欧を知らずして欧州を語るなってよく眼上の方に言われたなー。それだけいわれていたのに僕はサラッとブタペストのみ。ヘレンドの陶器/トカイ貴腐ワイン/マザーグース/Mother Gooseの羽毛布団で終わらせて、ついチェコ/Czechやポーランド/Polandを満喫してしまいました。乗馬やってる今なら大自然の中モウコノウマ/蒙古野馬の群れを観に行ったり色々あるんでしょうが、さーせん。
で、なんでそんな話申し上げたかといいますと、マンガリッツァ豚はハンガリーの国宝とも称される食材なんです。マンガリッツァ豚というのは見た目は羊みたいなカーリー/curlyなくるくる毛に覆われた豚の品種のことなんですけどね、気温の高低差がハンガリーと同じく夏と冬で50度前後ある北海道十勝も純血飼育に成功しましてその豚を友人がオーダーしてくれたというわけです。ちなみにハンガリーのマザーグース/Mother Gooseの羽毛布団も夏涼しくて冬温かいのは同様の寒暖差にマザーグース/Mother Gooseが順応したからです。
血統としてはイベリコ豚と近いらしいんですが、要は脂肪の融点がめちゃくちゃ低くて血液サラサラオレイン酸たっぷりの脂肪分の甘さも満喫できる市販の豚の3倍の飼育期間を経て10倍以上の価格で卸せるっていうそんな豚の脂身部分をたっぷり使われた回鍋肉/ホイコーロー。
嬉しいのがほんとさすが一級のプロって感じで、ちゃんと皮のゼラチン質部分を残した上で縦にスライスしてあること。食パンでいえばパン耳の上部にのみ皮が残っているっていうことです。この皮がねー、炙ってそれでも毛根ぎっちりなんで1本1本丁寧に骨抜きのように毛抜きしないといけない、超絶手間なわけです。太い毛1本あったら本当に興醒めしてしまうんで。中華くらいですね、豚肉でここの皮を使おうとするのは。食材に対する貪欲さではやはり中国人には負けます。
この1mmもない皮部分を残すかどうかで別次元の料理になるのが東坡肉/トンポーロウを筆頭とした中華豚肉料理の骨子だったりします。
で、回鍋肉/ホイコーローといえば甜麺醤/テンメンジャン必須ですが、菰田シェフのこの回鍋肉/ホイコーローは甜麺醤/テンメンジャンを必要としません。油も鍋にしきません。なぜか?マンガリッツァ豚の脂身で勝手に炒まるから、そしてマンガリッツァ豚の脂身が充分に甘いから。
今日のコースでは金華豚→加藤ポークと豚肉を堪能させて頂いてますが、やっぱり違いますよね。
本当に余計な脂の抜けた脂身の旨味が美しい。
コニャくにゅジャクジャク× 3、ごっくん。
あー、美しく美味い。
キャベツも甜麺醤テンメンジャンも入ってないのに確かに回鍋肉/ホイコーローしてる。
この美しくとなぜ申し上げたかといいますと、一緒に入っている赤と緑の万願寺とうがらしの噛んだときの皮の厚みとマンガリッツァ豚の皮の厚みが同じに揃っているから。
ここで厚みを合わせてくるのが最高に美意識感じるんですね。
見た目は王毅将軍×伊武雅刀÷2なんですが、なんて女性的な繊細な感覚をお持ちなんだろう、、、。
お肉についた余分な脂を器の端につけて落として、落ち切ったところに
コニャくにゅジャクジャク× 3、ごっくん。
コニャくにゅジャクジャク× 3、ごっくん。
うっひゃー、、、美しい。
足が早い赤い万願寺唐辛子を揃えるのも大変なのに、きっと同じ造り手の万願寺唐辛子なんだろうなー、そうかー、唐辛子の身の厚みと豚皮の厚みをこうも上品に合わせてくるか、これは感嘆。
で、一晩空けて前日に頂いたコースを思い出して気付いたんですよね。
この回鍋肉/ホイコーロー、あともう一段だけ美味しくなるって。
たぶん菰田シェフも気付かれてるんじゃないかな?
菰田シェフのこのお店の戦略って、日本人が作る日本人に好かれる極上中華っていうだけでなくて、さらにデート時の女性に喜ばれる、洗練されたカップルやメンバーがカウンターや個室でワイワイやるお店じゃないですか?もちろんお近くお住まいのご家族利用もあるとはいえ、です、
日赤通りのお店ってやっぱりそうですもんね。
え、違う?
だとしたらスルーくださいって感じなんですけど、それを前提に1つの世界レベルの料理としてあの回鍋肉/ホイコーローを見つめると、下に溜まってる脂が不必要だなと気づくんです。
お肉などの食材の下のほうの部分があの溶けた大量の脂の中に浸るの嫌だなと。
これは僕の好みに近い話かも、いや違うな、無意識のうちにお肉や野菜を口に入れる前に、お肉を器のへりにつけてぬらぬらについてる溶けた脂を流し落としていた自分を思い返すとやっぱり外側の脂はいくらマンガリッツァ豚の美味しい脂100%であろうと、あの高次元に完成された調和の中では異音/noiseでしかないからです。お皿に脂がほとんど垂れずにあの回鍋肉/ホイコーローが出てきたら、それがあのお皿の完成形だと思います。
溶けた脂分は厨房でとっておいて後日の別料理に、その場で明らかにまだ食べたそうな来店者がいたら別盛りで提供したほうが双方にとって良いと思います。白米にはあの脂をかけて食べるのがさーっていうのは、ここまでのコースの流れが急に男性的になりますからね。
多くの高級中華料理店は最後の麻婆豆腐で急にこれをやります。
ゼラチン質の皮の旨みと脂が8-9割抜けた脂身の旨味と赤身の旨味とあの万願寺とうがらし達だからこそあのひと皿は高次元で成立するかなと思うわけです。
うん、2-3日経過して改めて感じます。この回鍋肉/ホイコーローはお皿に一滴も溶けた脂が滴れてないくらいのほうが見た目も味も舌触り感もコースの流れとしても合うと思います。
逆に町中華や本場四川の高級中華料理店ならあの溶けた脂はもっと遥かに低いランクの豚肉でもたっぷりゴリゴリ使うのが正解。
ただ、菰田シェフの店舗展開の緻密な戦略に加えてこれだけ洗練された繊細な構成をここまで堪能してきた僕としてはあの下に溶けて溜まった脂には違和感を強く感じてしまうんでよね。
断っておきますが、現時点で充分美味しいので多くの方にはただ×2絶賛されるはずですが、僕眼線ではあの点だけが唯一あのお皿で惜しいなと思うわけです。
僕は「好み/嗜好」の話よりも「絶対的/普遍的」な視点での話が好きで、もしあの下の脂がなければ、味の項目が一気にあと0.4pt上がるそれくらい大きな差だと考えています。
いずれにせよ、切り方/味付け/食材のバランスなどは1つのスタイル/Styleとして紛れもなく完成していて、世界トップレベルの完成したお皿に向けてのラストワンマイル/last one mileの話です。
このレベルのお料理を頂くとどうしても「完璧なひと皿」から逆算して見てしまいます(/ _ ; )
〈デザート〉
パッジョンフルーツソースがかかったマンゴープリン。
今日のコースの締めとして、静かに幕引けです。
これだけ満喫して税込34,000円/人程。
サービス料はNothing.
お茶のペアリング(6,000円/人)も興味深かったですが、確かに合っていましたが僕の基準でのマリアージュ/mariageまでは届かず「合うねーっ!」ていう感じ。でもソムリエの方々が中国茶もしっかり研究されているのはよく伝わります。
ならワインのほうが楽しめるなと思いました。
ふぅ、満足×2。
コースの中でとても印象的なひと皿が複数あるのでお得感すら感じます。
この総合ポイントは日本人に好かれる高級中華料理というジャンル/genreの中でのものとします。このレベルになると「本場四川料理と比較して〜」というくだりは一切必要なくなります。
お昼はお一人様でも友人とでもご自由に、ただ、夜はあのカウンターに3人横並びはないと思うので、やはりデートにお勧めです。
ここは抜け道にも使われるのでタクシーもよく捕まります。
2件目は西麻布/広尾/恵比寿/表参道/渋谷とどこでもどーぞ。
※ソムリエ達もまだお若くリア充なのに色々とわきまえていて、菰田シェフが性格の良い実力者達を集めているのがよく理解できます。
※個室もあるので会社スタッフ達とわいわいするのもアリです。
※カウンター内のメジャーなワイン(オーパスワンやサッシカイア)などのボトル展示はワイン好きからしたら逆効果(ワインペアリングお願いする気が減退するという意味)なのでお勧めしないです。
※全く同じ食材というわけではありませんが、ランチはやはりより一層お得です。